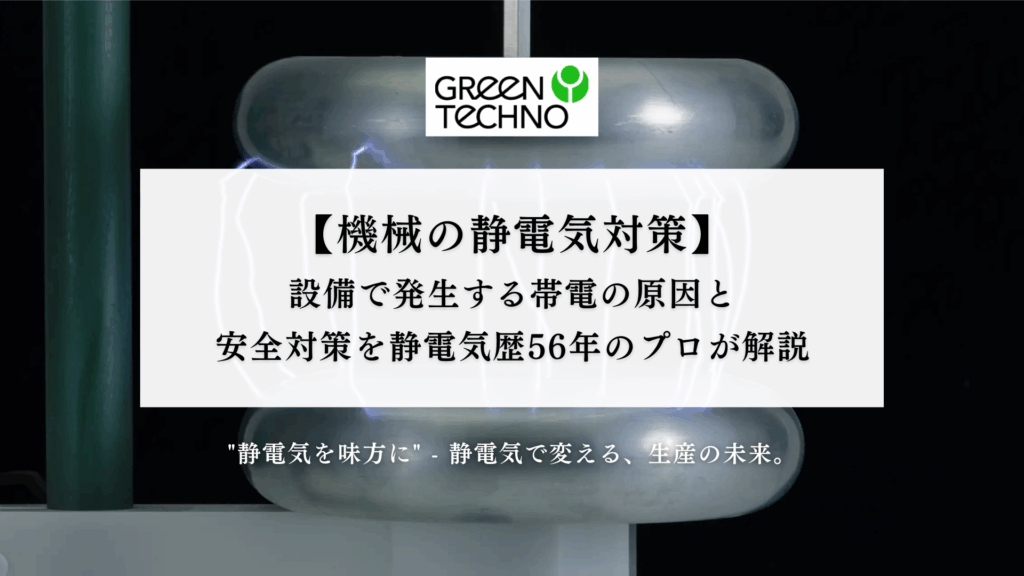
< 記事の信頼性について >
本記事は、静電気技術の専門メーカーである株式会社グリーンテクノの担当者が制作・監修しています。
株式会社グリーンテクノは、1969年創業。
静電気の「発生・帯電・放電」に関する装置の研究開発・製造・販売を一貫して行う専業メーカーとして、50年以上にわたり、製造業・研究機関・大学など多様な分野の課題解決に貢献してきました。
実際に現場での課題対応を行っている担当者が、導入経験や技術知見をもとに執筆しており、高い技術的信頼性と実用性を担保しています。
製造現場では、静電気による誤動作、異物の吸着、製品の損傷など、様々なトラブルが発生します。こうした静電気への対策は、品質管理や安全確保の観点から非常に重要です。
一方で、私たちグリーンテクノは、創業から55年以上、静電気をあえて発生させ、制御して活用する機器を開発・製造してきた企業です。
静電気を“使いこなす”立場だからこそ、その発生メカニズムや制御方法、そして対策の本質を深く理解しています。
本記事では、そうした技術的な知見をもとに、機械設備における静電気の発生原因と、その正しい対策の考え方を技術者・現場担当者向けにわかりやすく解説します。
まず静電気の発生原理は「電荷の偏り」です。
正確には、「静電気=電荷の偏り“がある状態”」です。
物体どうしが接触・摩擦・剥離すると、素材の組み合わせや条件によって電子が一方から他方へ“移動”します。
その結果、電荷のバランス(=電荷分布)が崩れた状態が生まれます。
ただし、偏りが生じた直後でも必ずしも問題にはなりません。
次のような条件で電位が高まりやすい/放電しやすいとき、機械・設備のトラブルに繋がります。
① 生成速度 > 漏洩・除電速度
乾燥・絶縁・アース不良・高速運転などで電荷が逃げにくい(蓄積する)状態。
② 瞬間的に高電位が立つ
例:剥離直後は静電容量が小さく電圧が跳ね上がる、静電誘導や人体帯電で一過性の放電(ESD)が起こる。
また乾燥・絶縁・アース不良・高速 などはこれを悪化させます。
ここからは具体的なトラブルとその原因を見ていきましょう。
どう起きる(原因):異なる材料が触れる/離れる過程で電子が移動し、双方に異符号の電荷が生じる。接触面積・速度・材料組み合わせが大きいほど帯電量は増加。
何が起きる(トラブル):表面の電界が強まり、微粒子の吸着やセンサーの誤検出、局所的な放電が発生しやすい。
放置リスク:外観不良・再清掃の増加、検出不安定化による小停止の多発、可燃性雰囲気では着火源になり得る。
ポイント:剥離直後のように静電容量が小さい局面では電圧が跳ね上がりやすく、瞬間的な放電(ノイズ)に注意。
どう起きる(原因):樹脂・塗装・防振部材・回転要素などで電荷の逃げ道が途切れると、生成された電荷が広範囲に残留する。
何が起きる(トラブル):装置各所で帯電のムラや点在する放電が起こり、対策の効きが不均一になりやすい。
放置リスク:誤動作の散発化・解析難度の上昇、歩留まりのじわじわ低下。
ポイント:接地は“有無”だけでなく導通の連続性(塗装・ベアリング・防振材の跨ぎ)が重要。
どう起きる(原因):低湿度では自然漏洩が減り、運転速度が高いほど帯電イベントの頻度と強度が増える。
何が起きる(トラブル):**季節依存(冬に悪化)や速度依存(増速で悪化)**が現れ、吸着・誤検出・放電が同時多発しやすい。
放置リスク:稼働率の低下、再作業・再検査の増大、品質ばらつきの拡大。
ポイント:目安はRH50〜65%。環境条件は装置側対策の“効き”にも影響する。
どう起きる(原因):歩行・衣服摩擦で人体が帯電、または近傍の電界で未接地の金属(浮遊導体)に電荷偏在→接触で放電。
何が起きる(トラブル):触れた瞬間の放電による制御系の瞬断・リセット、電子部品(IC)の潜在損傷。
放置リスク:原因が見えにくいまま散発不良やラインダウンに繋がる。
ポイント:EPA(静電気保護区域)の運用・未接地金属の管理など人と周辺物の一体管理が要。
| 吸着・汚れ:主に①+③(+②)の組合せで発生し、外観品質や清浄度を直撃 |
| 誤検出・誤動作:①の放電や④の一過性放電がトリガで、②が背景にあると散発化 |
| 静電破壊(ESD):④(+①+③)で顕在/潜在損傷を生み、信頼性低下に直結 |
| 火花・火災:可燃性雰囲気で①+③(+②)が重なるとリスク上昇 |
| 稼働・歩留まり:上記が重なり合うことで連鎖的に悪化する |
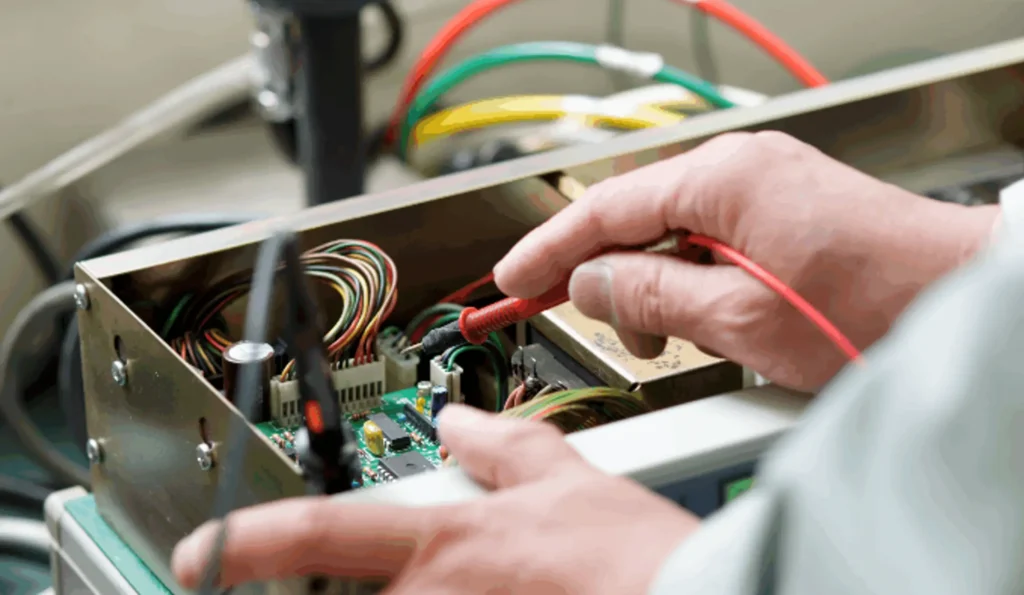
静電気対策の基本は「逃がす」「抑える」「持ち込まない」の3つです。
導体部分を確実に接地すれば、電荷は地面へ逃げます。
アースは1か所だけではなく、設備やフレームごとに点検し、確実に導通しているかを確認する必要があります。
湿度が高いと空気中の水分が導電性を持ち、帯電が中和されやすくなります。
加湿器や空調で環境管理を徹底することが重要です。
帯電防止靴・導電性マット・リストストラップを活用し、作業者自身が帯電源にならないようにします。
静電気管理区域(EPA)の設定も有効です。
樹脂やフィルムには帯電防止剤を塗布したり、導電性フィルムに置き換えることで、帯電の蓄積を防ぎます。
「ゼロにする」のではなく「コントロールする」視点も重要です。
帯電を利用すれば、搬送効率や機能性を向上させることも可能です。
「対策しているはずなのにトラブルが出る」というケースは珍しくありません。
これは、帯電のメカニズムが複雑で、原因を一度の観察で特定しにくいためです。
このような場合は、
『実際に帯電状態を再現する』
ことで原因を追求することができます。
当社グリーンテクノでは、静電気を「発生させる」装置を保有しており、あえて帯電させてトラブルを再現・検証する取り組みを支援しています。
実施する対策の効果を実証し、トラブルの根本解決を見据えることができます。

静電気はリスクだけでなく「利用価値」も持っています。
意図的に帯電させることで、製造工程の効率化や新しい機能の実現につながります。
例えば、
| 帯電固定:フィルムやシートを帯電で仮止めし、搬送や積層を安定化。クリップ不要で異物混入リスクも減少。 |
| 静電塗装・植毛:帯電した塗料や繊維が均一に吸着。塗着効率が向上し、材料ロスも削減。 |
| 帯電フィルター(エレクトレット化):フィルターに帯電処理を行うことで、微粒子を効率よく捕集。空気清浄機やマスクに応用。 |
| 静電選別:粒子や樹脂ペレットを帯電特性の違いで分離。リサイクルや品質選別に活用可能。 |
| 静電掲示:ポスターやシートを糊を使わず仮固定。食品・医薬品現場では異物混入防止に有効。 |
私たちグリーンテクノは、静電気を“使う技術”として、発生・制御・除電・測定までワンストップで支援しています。
対策も重要ですが、もし活用できるかも?と思った方は、お気軽にご相談ください。
静電気は、製造機械や設備の誤動作や不良の原因となる厄介な現象ですが、正しく対策を行えば、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。
ただし、対策の効果は「導入して終わり」ではなく、現場でのテストや再現確認を通じてはじめて実効性が見えてくるものです。
グリーンテクノでは、もともと静電気を“使う技術”の装置開発を行っていますが、その知見を活かし、静電気トラブルの再現試験や帯電状況の可視化のために製品をご活用いただくケースも増えています。
「実際に帯電させてみて、除電器の効果を検証したい」「製品の静電気感受性を確認したい」――そんなニーズがある場合も、当社製品と技術支援をご活用いただけます。
機械や工程ごとの静電気対策にお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせ
お問い合せ、資料請求などお気軽にご連絡ください
